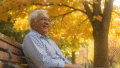「固定観念の強い人は病気になりやすい」
京都大学の研究チームが国際老年医学会誌に発表したアンケート(2019年から2020年にかけて高齢者2万6000人に実施)によると、「家の外で働くのは男性の役割」「家庭を守るのは女性の役割」といった性別に関する固定観念の強い人は、そうでない人に比べて心の健康状態が悪い傾向にありました。
固定観念が強いと、精神的ストレスから健康にも悪影響を及ぼすようです。
固定観念にとらわれる
日本の社会では、子どものころから潜在意識として、「男らしさとは」とか「女らしさとは」という観念を植え付けるような教育がありました。たとえば、ランドセルの黒は男の子、赤は女の子みたいに常識として暗黙の了解みたいなものです。
また、日本の社会では、「男は強くならなければならない」「男は弱音を吐いてはいけない」「男は出世しなければいけない」「女は良妻賢母で家庭を守る」「女は会社ではアシスタント業務を行う」のように、性別による役割に対して「こうあるべき論」が支配し、無意識の偏見がありました。
私が社会人になった頃は、職場で女性が男性にお茶を出し、机の上にある煙草の灰皿を掃除する光景が見られました。あの頃はきっと、凝り固まった価値観が「嫌だな」と感じていた人もいたはずです。
固定観念からくる呪縛
戦後に生まれた今のシニア世代は、子どものころから受験など常に激しい競争のなかで育ってきました。会社に入ってからも「出世競争に勝たなければいけない」「高収入を得て社会的評価を得るべきだ」といった「男らしら=競争に勝つ強い男」を求められ、その呪縛にとらわれていました。
50代60代の意欲低下は、こうした凝り固まった価値観の影響から、定年を境に期待と現実のギャップによる精神的ストレスで引き起こされるようです。
近年は価値観が多様化し、個を重視する時代です。古い価値観に執着して「こうあるべき論」を振りかざすと、自らの人生を生きづらくします。
環境変化に柔軟な対応
60歳を過ぎ、セカンドキャリアとして再雇用や嘱託で働き続けると、職場での立場が急激に弱くなり、給与も大幅に減少します。
パーソナル総合研究所が2021年に行った調査によれば、定年後の再雇用者の年収は定年前に比べ平均して44%も低下するようです。
また、定年前とほぼ同様の職務でありながら権限や責任はなくなります。
そのため、自分のプライドと仕事や待遇にギャップが生じ、「仕事にやりがいがない」「自分の働きが認められていない」「元部下たちが仕事の相談がなくなった」などの自己喪失感から仕事内容に不平・不満を抱え、働く意欲が低下するようです。
この場合も、「こんなはずじゃない。こうあるべきだ」といった固定観念が強く影響しています。
固定観念から脱却
セカンドキャリアでは、「こうあるべきだ」という固定観念に執着するあまり、周囲の反感を買い、孤立してしまう人が多いようです。孤立すると、これまでのキャリアで築き上げた人間関係や社会的役割を失い、孤独感や疎外感を感じることになります。
そうならないためにも、凝り固まった固定観念を捨て、新しい価値観を受け入れることが大切です。
私も現役時代は、「こうあるべき論」に執着するところがありました。自分の価値観を、相手に一方的に押し付けたこともあります。
今では、新しい価値観を受け入れ、柔軟に対応しています。家事も妻と役割を分担し、たまに料理をつくるなど楽しい時間を過ごしています。
まとめ
現代社会は、変化のスピードが非常に速く、従来のやり方や価値観が通用しなくなっています。また、固定観念に縛られると、視野が狭くなり、物事の本質を見失うことにつながります。
「こうあるべきだ」と自らの行動に対して、必要以上にプレッシャーをかけたり、思い通りにならない相手に対して、腹を立てたり、批判的になることは自分や他人を必要以上に責め、精神的ストレスに苦しむことになります。
セカンドライフでは、こうした固定観念を手放し、それぞれの個性や資質に合った生き方を尊重することが、よりよい人間関係を築くことにつながり、きっと笑顔あふれる日々が送れるはずです。